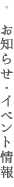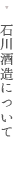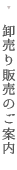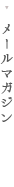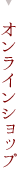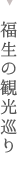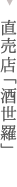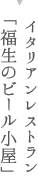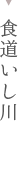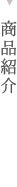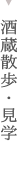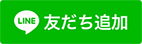二刀流の挑戦者たち:日本酒とクラフトビールの饗宴
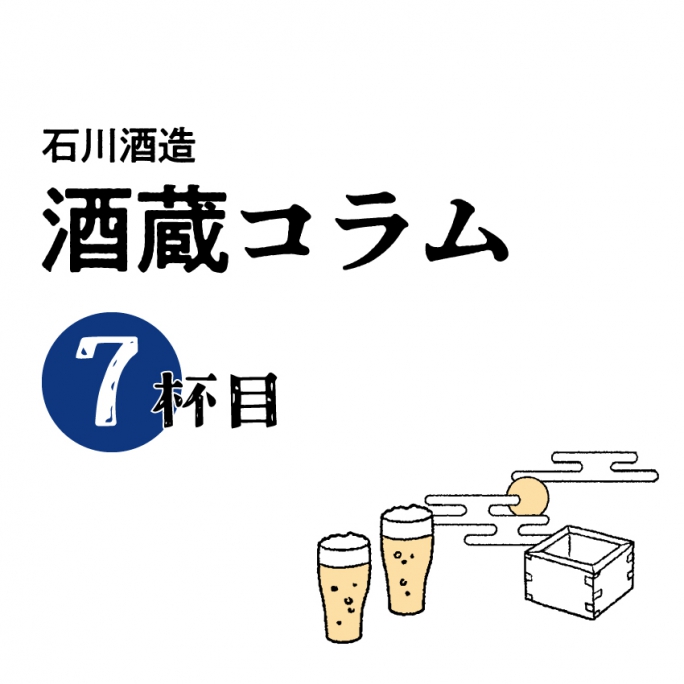
東京の福生市で、160年以上にわたり酒を醸し続けている石川酒造です。
日本酒好きの皆さまには、石川酒造は伝統的な日本酒「多満自慢」を造る酒蔵として知られています。
しかし、蔵の扉を開けると、そこにはもう一つの顔があるのですが、ご存知ですか?
日本酒造りで培った発酵の知恵と、清らかな水へのこだわりを活かし、クラフトビール「多摩の恵」「TOKYO BLUES」を醸しているのです。
一つの蔵で、日本酒とクラフトビールの両方を手掛ける、全国的に見ても数少ない「二刀流の挑戦者」なのです。
(逆も然りで、ビール好きの皆さまに、日本酒も造っていることを驚かれることもありますが。)
このコラムでは、私たちがなぜこの挑戦に挑んだのか、そして、日本酒とクラフトビールという二つの文化が、どのようにして互いに影響し合い、新たな美食の世界を切り開いているのかをお話しいたします。
<日本酒造りの知恵が活きる!クラフトビールとの共通項>
日本酒とビール。その発酵方法は近いようで、遠いような、実は違う点が多くあります。
ここでは難しいので深くは触れませんが、日本酒は並行複発酵(米に含まれるデンプンの糖化と、酵母によるアルコール発酵が同じタンクで同時進行する)、ビールは単行複発酵(麦芽の酵素がデンプンを糖化した後に、酵母によるアルコール発酵が行われる)ということが大きな違いです。
では、石川酒造にとってどこが共通項なのか。
それは、酵母(微生物)と水です。
酵母
もちろん、日本酒用の酵母とビール用の酵母は違いますが、同じ微生物。発酵のプロである酒造りの最高責任者「杜氏」は、発酵のプロセスにおいて、なぜ上手くいったのか、またはいかなかったのかを、その知識で解明することができるのです。
水
石川酒造は水に恵まれています。
多満自慢を造る際に使用する秩父山系の伏流水である自社地下天然水は、ビール造りにおいても、その清らかさでクリアな味わいを生み出しているのです。
<先祖の想いを受け継いだ、クラフトビール「多摩の恵」>

1994年(平成6年)に、それまで大手メーカーしか基準を満たすことが厳しかった「ビール免許取得のための年間最低製造量」が2000kL以上から60kL以上に規制緩和され、醸造のハードルが下がったことで、醸造が可能となりました。
1887年(明治20年)に一度、ビール醸造を行った歴史を持つ石川酒造の敷地には、当時の醸造道具であるビール釜が残っています。
明治時代では、まだ時期尚早だったようですぐに醸造を諦めましたが、この法改正を受け、14代当主の叶えられなかった想いを実らせるチャンスが来た!と、各国、各地で視察を行い、1998年(平成10年)にビール醸造を復活させることができました。
中でも、視察に行った先のドイツ、ベルギーのビール醸造所での印象がその後に大きな影響を与えています。
ヨーロッパのビール醸造は歴史が深く、日本酒の蔵元のような雰囲気を持つということ。
多くのビール醸造所にはビアレストランが併設されていて、地元の人たちが、その地域で作られたビールを飲みながら世間話をしている風景が、どの町に行っても見られました。「地域のコミュニティーの形成に役立っている」という光景が後に、石川酒造のビール復活の基軸コンセプトになっているのです。
ということで、多摩の恵の誕生とともに、併設レストラン「福生のビール小屋」も誕生しました。
明治期から、日本酒とビールの二刀流に挑戦していて、現在はものづくりとしての製造業と、お酒を楽しむ場を提供する飲食業との二刀流も成し得ているということでもありますね。
多摩の恵の名について
石川酒造界隈では社長の奥様のお名前から来てるのでは!?という噂がまことしやかにささやかれておりますが、残念ながら違います。
長くなるので詳細は割愛しますが、ひもといた歴史と現在の多摩地域がもたらす恵みについてを考証してたどり着いた「皆さまの食卓を陰で支えるお酒でありたい」という想いが込められています。
多摩の恵、その味わい
多摩の恵は通常品と季節仕込み品とがあり、せっかくなので、ここではいつでも飲める通常品の紹介をいたします。
このシリーズは、ヨーロッパを旅した方には「懐かしい」とよく言われます。なぜなら、日本で飲みやすいようにはしていますが、欧米の伝統的なスタイルを踏襲し、基本を外さないレシピで醸しているからです。
◆ペールエール
ホップの香りが爽やか!軽やかな口当たりが特徴。
◆ピルスナー
世界シェアNo.1の皆さまに馴染みのあるスタイル。素材の味わいを活かし、仕上げています。
◆デュンケル
深いコク、麦芽の香ばしい風味。なによりも、やわらかな甘みが特徴です。黒ビールの概念を変えるかもしれないまろやかな甘さ!
上記の他、ブルーベリーエール、ヴァイツェン、ベルジャンウィットなどを不定期で醸造しています。
<新たな挑戦!TOKYO BLUESシリーズ>

多摩の恵で培った技術を活かし、こちらはオリジナルレシピで醸造しています。
東京の地で醸す、東京の名を冠した、真の東京クラフトビールとして2015年(平成27年)に満を持して誕生。
洗練されていて革新的。東京らしい原料を取り入れた、新しいビアスタイルにも挑戦しています。
このビールは東京の魂を揺さぶるビール、ブルースのように人生に寄り添い、高速で走り続ける心を解き放ってくれる。まさに、東京のために生まれてきたビールです。
TOKYO BLUES定番品
◆セッションエール
鮮烈な柑橘の香り!印象的な苦味。飽きずに飲めるドリンカビリティの高いビール。
◆ゴールデンエール
確かな飲み応えのある、フローラルな香りが心地よい、綺麗な味わいのビール。
◆シングルホップウィート
ドイツ伝統の白ビール、ヴァイツェンスタイルの味わいを東京の感性で仕上げました。華やかさと品の良い苦味が特徴。
<違いを知り、共通点を楽しむ:日本酒とクラフトビールの饗宴>
日本酒とクラフトビールは、一見すると全く異なる飲み物です。しかし、どちらも米や麦といった穀物を原料に、水と酵母の力で醸される、発酵の芸術。
石川酒造の敷地内にあるレストラン福生のビール小屋では、この二つの飲み物を、料理と共に楽しんでみましょう!
例えば、多満自慢の純米酒と、多摩の恵の飲み比べ。
原材料の水の綺麗さは共通していますが、通純米酒は米の優しい旨味があり、多摩の恵は麦芽の心地よい香味を感じます。
この二つ、意外にも、同じ料理に合わせても、異なる表情を見せてくれるんです。
例えば、地元の食材を使った野菜料理では、純米酒の米の旨味は野菜本来の美味しさを引き立ててくれて、ビールの香味はお料理に華を添えるよう。
日本酒とビール、どちらかが優れている訳ではなく、どちらもそれぞれの良さがあり、その時の体調や気持ち、お料理に合わせて選ぶ楽しさがあるのです。

石川酒造で体験できる、日本酒とクラフトビールの飲み比べ。
多満自慢と多摩の恵、さらにはTOKYO BLUESの飲み比べは、他ではできない特別な体験となるでしょう。
毎月第4週の土曜日と連なる日曜日に開催される、特別な酒蔵見学で、日本酒(あるいはビール)の造り方を知り、試飲でその味わいを確かめる。
そして、レストランで料理と共に飲み比べる。
見学のテーマは毎回違うため、日本酒について掘り下げたり、酒造りの体験ができたり、ビールの醸造や原料について深く学んだりと、月毎に異なる体験・発見をすることが可能です。
これからも石川酒造は、二刀流の挑戦者として、日本酒とビールの垣根を越え、皆様に新たな美食の体験をお届けできるよう、日々精進してまいりますので、ぜひご来場くださいませ!